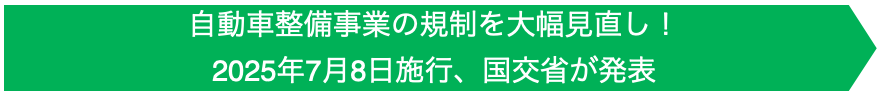
国土交通省は令和7年7月8日、自動車整備事業を取り巻く環境変化に対応するため、7項目の規制見直しを公布した 。技術の高度化と人材減少という課題を背景に、事業者の負担軽減と業務効率化を目的としたこの法令改正は、業界に大きな影響を与えると見られる 。
認証工場の要件緩和とデジタル化
認証工場が備えるべき機器の要件が見直された 。これまでの義務付けから、タイヤの傾きを測定する機器(トーインゲージ、キャンバ・キャスタ・ゲージ、ターニング・ラジアス・ゲージ)は設置が不要となる 。また、小型・軽・二輪の整備に使用しない機器も、普通(大型・中型)・大特を扱う工場を除き設置義務がなくなる 。エンジン・タコテスタやタイミング・ライトといった機器も、整備用スキャンツールがあれば設置不要となった 。一方で、電子制御の整備に不可欠な「整備用スキャンツール」の設置が必須化される 。これは新規認証時から適用される 。
指定工場の工員数緩和と検査員要件
大型車を扱う指定工場では、省力化設備等の一定の要件を満たした場合、最低工員数が5人から4人に緩和される 。これにより、人手不足に悩む事業者の負担が軽減される 。また、自動運転車(レベル3・4)の検査は、電子制御に関する高い専門性を持つ1級自動車整備士に限定される 。この改正は令和11年4月1日に施行される 。
人材育成と業務効率化を後押し
若者の整備士離れを食い止めるため、資格取得に必要な実務経験期間が短縮される 。2級自動車整備士は3年から2年へ、3級自動車整備士は1年6か月に、特殊自動車整備士は2年から1年4か月に短縮される 。また、研修・講習のオンライン化も解禁され、整備主任者や検査員研修の座学がオンラインで受講可能になる 。紙の備え付けが必須だった点検整備記録簿も、電子的な保存が可能となり、整備工場の業務効率化に繋がる 。
点検方法のデジタル化
点検整備の方法もアップデートされた 。日常・定期点検の一部項目で、目視に代わりスキャンツール等による確認が認められる 。これにより、ブレーキ・ペダルの踏みしろや、排気ガス再循環装置の機能などの点検作業時間が短縮される見込みだ 。この改正は令和7年10月8日に施行される 。



